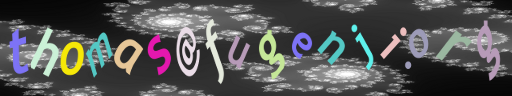『TeX Live を使おう』に関して
そもそも僕が TeX / LaTeX というものを使い始めたのは、もう20年程も前のことになる。TeX / LaTeX の存在自体は、大学に入る位の頃から耳にしていて、大学の学生実験が始まった年に、なんとかレポート作成に使えないものか、と思い始めたのである。しかし、当時の僕が持っているのは、16 ビットの PC98、しかも HDD や増設メモリなど買えそうにない経済状態で、ネットへの接続もままならない状態だった。
当時の僕の周囲には、既に 32 ビットの PC98 に大型の EMS ボードを挿し、モデム経由で NIFTYSERVE 等を使っている同期が何人かいて、彼等に相談してみたところ、何日かして、何枚かの(当時はまだ 5 インチだった)フロッピーディスクを渡してくれた。早速帰宅して中身を見ると、go32 を利用して動作する、いわゆる Eastwind 版の TeX 一揃えが入っていた。分からないながらに簡単な文書を書いて、初めて手元の環境で処理して dviout で表示したときの衝撃は、未だに忘れられない。自宅での出力環境は24ピンのドットインパクトプリンターだったけれど、初めて、
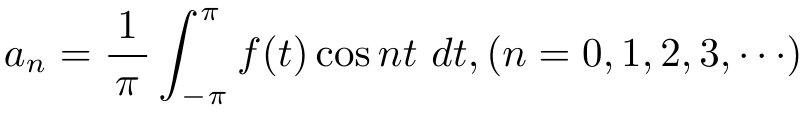
大学3年になった年、僕の居た大阪大学は、OS X の源流になったあの NeXT を400台導入した。記念式典にはあの Steve Jobs が直々に大阪にやってきて、僕等の目の前であの天才的なデモンストレーションをしたのだった……そして、この NeXT は、僕の勉学におけるコンピュータ環境を劇的なまでに変革した。なにせ、400 dpi のレーザープリンタが接続された pure な Postscript 環境(NeXT は画面表示すら Postscript で行っていたのだ!)、しかも firewall 経由ではあるにせよ、ネットワーク環境もちゃんと使える状態のものを、学生が好きに使えるのだ。そしてこの NeXT には、ASCII 日本語 TeX がインストールされていた。
この時期から、僕は TeX / LaTeX 以外の手段で論文を書いたことがほとんどない。学部・修士の論文も、そして勿論学位論文も TeX / LaTeX で書いた。特に学部の卒論は、グラフは NGRAPH で出力した PS ファイルと、一部の人に利用開放されていたスキャナで取り込んだ画像を LaTeX + epsf で配置してレーザープリンタで出力した、完全な LaTeX document だった。まあ、あの環境で、これをやらなきゃあ、あまりに勿体ないというものではないか。
そんなことをやっているうちに、寮の文系の友達つながりで、文系の学生達から「TeX ってどうやって使うの?」と聞かれることが多くなった。当時彼等は、PC98 や NeXT 上のワードプロセッサで論文を執筆していたのだが、バックアップを取る前に落ちることが頻繁にあって、相当痛いメに遭っていたらしい。質問者が二桁を超えたので、これは何処か借りて講義でもした方が早いなあ……と思い、大学の情報処理教育を行っている部門に相談してみたら、テキストの製本等の面倒はみるから、是非やって下さい、と言われた。さあ、そこからが大変である。春休みを潰してテキストを書いた。記号に関する説明で、当時 TeX 使いの間で must item と言われていた『LaTeX 美文書作成入門』の表を引用する必要が生じて、NeXT 上から電子メールで著者の奥村晴彦氏に許可依頼を出したら、
「教育目的の引用は著作権法上許諾は不要です。どんどん使っちゃって下さい」
という、非常にシンプルな返信が返ってきた。これに勇気付けられて、結局全学規模になってしまった TeX のセミナーをし仰せたのだった。
まあそんなわけで、TeX / LaTeX 及びその周辺の人々には、僕は様々な意味で恩恵を受けているわけだ。しかし、正直言って、その恩を返せているとは、とてもじゃないが思えない。僕等の業界では、先達に受けた恩は後輩に返すことになっているので、この恩は後輩に何らかのかたちで返さなければならないわけだ。
しかし、ネット上での Q&A の類には、僕は限りなく絶望に近い印象を持っている。最近はどうも、自らの課題・問題点をまとめた上で、必要な情報を探索する能力というのが、日本人全体の中で、急速に衰えているような気がしてならないのだ。昔の電子ニュース華やかなりし頃だったら、void 氏や lala 改め lala-z 氏にボロカス言われるわけだけど、今はそういう「親切な」人はほとんどいない。たまに僕がキツいことを書くと「荒らしですか?」とか開き直られたりする。阿呆か。まあそんな感じなので、僕自身も最近はそういうコンテンツを作ることはほとんどないわけだけど、TeX Live に関しては、これから大学で論文を書く人とか、科研費出そうと思って書類書かなきゃならない人とか、まあ結構需要があるのだろうから……ということで、件のコンテンツを作成した次第だ。徐々に拡充していくつもりである。