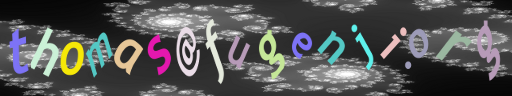emath を入れる
相変わらず、GNU Emacs で書きものをして LaTeX でタイプセットする機会は頻繁にあるわけだけど、最近は解説のようなものを書く頻度が増えているので、たとえば数学の教科書などにあるような書き方をしたい、と思うときがある。
まさにこういう目的で作られたのが emath である。どのようなものなのかは、http://homepage3.nifty.com/emath/pdf/sample.pdf をご覧いただければお分かりいただけると思う。この emath は非常に多機能だし、便利だろうと思うのだけど、僕は今迄手を出すのに二の足を踏んでいたのである。
それは何故か、というと、この大熊一弘氏によるマクロ集は、コマンドが日本語ローマ字書きのものが多いので、書きながらさくっと使う上での直感性がイマイチなのである。では、50音索引付きのマニュアルのようなものがあるのか、というと、先の sample.pdf の基になった原稿から生成した sample.idx を mendex に読ませて索引を生成させればいい(上のリンク先の PDF はそうなっている)わけだけど、これは目次用のインデックスで作成した索引なので、充実した索引にするためには更にインデックスを付け足していく必要があるだろう。しかし、その作業の量を考えると……これは結構大変そうである。
まあ、でも、無いと困るんだから、これは作るしかなさそうである。こうやって僕のお盆休みは順調に潰れていくのだろうか、と、少し鬱な気分になるわけだけど、まあ、後でやっておくことにしよう。
インストール自体は単純である。まず emath の index page から emath のページにアクセスし、この「入口」からアーカイブにリンクされたページを見る。「スタイルファイル」の「丸ごとパック」のページから、基本となるアーカイブを取得するのだが、ここで ID とパスワードを要求される。これは「入口」に書いてある(すぐ暗記出来る程度の単純なものである)ので、それを入れればよろしい。アーカイブ取得後、同じく「スタイルファイル」の下にある「修正パック」と「実験版」の最新のアーカイブを取得する。
まず手近な作業用ディレクトリを確保し、emathf??????c.zip を展開する。sty.zip, doc.zip, pdf.zip の3つのアーカイブと readme が出てくるのだが、これらを LaTeX のファイルを置くべき場所に展開する。僕の場合だと、
のように$ cd /usr/local/texlive/texmf-local/tex/latex/
$ sudo mkdir emath$ cd emath$ sudo unzip ~/tmp/emath/emathf??????c/sty.zip
$ sudo mkdir -p /usr/local/texlive/texmf-local/doc/emath
$ cd /usr/local/texlive/texmf-local/doc/emath$ sudo unzip ~/tmp/emath/emathf??????c/doc.zip
$ sudo unzip ~/tmp/emath/emathf??????c/pdf.zip
$ sudo /usr/local/texlive/2011/bin/x86_64-linux/texhash
「修正パック」も「実験版」も、同様の手順で(「丸ごとパック」のファイルを上書きするようにして)入れればよろしい。大熊氏も警告されているようだが、必ず「丸ごとパック」→「修正パック」→「実験版」の順に作業を行うこと。なお、Perl スクリプトのインストールに関しては、emathWiki の『perl との連携』に詳しく説明されているので、そちらを御参照いただきたい。
……と、ここまでやってから、あーそう言えば一番面倒な作業をしてないじゃん、と思い出した。emath は前提として必要としているスタイルファイル・クラスファイルが結構な数あるのだけど、それらをチェックしながら入れなければならないのだ。詳細は、『math に必要なスタイルファイルなど』を参照されたい。
というわけで……これから TeX Live のファイルとバッティングしないように、この必要なファイルのインストールをすることになりそうだ……
というわけで、今さっき作業を終えたところである。僕の環境(TeX Live 2011)の場合は、
- EMwallpaper
- eclarith
- eclbkbox
- hhdshln
- jcm
- kunten2e
- mbboard
- random.sty
- ruby.sty
- uline--
しかしなあ、うーん……この emath って、おそらく中高の数学の先生とか塾講師なんかが使うんでしょう?まあ、数学専攻の人だったら LaTeX を使うことにはあまり抵抗はないかもしれないけれど、tfm や pk フォントの生成とか、分からない人はどうするんだろう。あと、おそらく DOS / Windows 以来の弊害かもしれないけれど、マクロ名が大文字小文字混在になっているところでトラブルが発生することが何度かあった(たとえば EMwallpaper とか)。これも、分からない人には理解し難いような気がする。そういう辺りを(分かっている人には面倒なだけなのかもしれないが)refine することが、今後求められるのかもしれない。