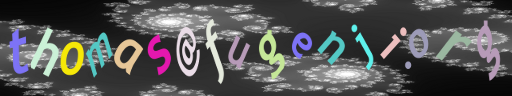昨日リインストールした Windows Vista が思ったよりも調子がいいので、ついついスケベ心が出て、色々と使えるようにしてしまった。
まずは TeX を使えるようにする。これは簡単で、角藤氏のW32TeX(正確には Ring Server に置いてある mirror)の収録ファイルを取ってきて、texinst2010 を使って展開するだけである。PATH を追加すればもう使える。
TeX が使えるとなると Emacs が欲しくなる。Emacs-23.3 の Windows binary を GNU から取ってきてインストールし、更に APEL と ddskk を入れる。たまに Twiitter を使うので、 twittering-mode を github から取ってきて入れてみる。UNIX 系 OS と設定の感じが少々異なる(当然だけどデリミタがバックスラッシュだったり、とか)ので最初は面喰らったが、フォントも好みに直して、書きものをするのには十分な状態にすることができた。
こうなると、今度は UNIX 系のコマンドセットが欲しくなってくる。Cygwin は入れたくないんだけど、unxutilsって開発止まってたよなあ……と調べると、"Gow – The lightweight alternative to Cygwin" なるパッケージが出ていることを知る。さくっと入れてみると、なかなかよろしい。ただし、bash 等はどうも動作が怪しいので、あまりあてにはしないことにする。
TeX 関係でいくつか ruby を使うものがあるので、Perl の前に ruby を入れておくことにする。ruby の公式サイトでは x86 x64 双方のバイナリを公開しているのだが、64 bit binary はどうもうまく動作しない。コンパイラのランタイムのせいかと思ったが、そうでもないようだ。面倒なので 32 bit 版をインストールした。
更に細かいところを brush up して、なんとか普段の使用に耐える状態になった、ようだ。とりあえず印刷時には Adobe のフォントを埋め込んで行うようにしたし……まあ、こんなところか。それにしても、Windows ってちっとも便利じゃないよなあ。どうして皆 Windows を使っていてストレスで「あーもう嫌!」ってならないんだろう。僕は DAW と DAW 上での VST の利用さえなければ、Windows なんか使っていやしないと思うんだけど。
この blog のエントリは、現在 Windows Vista 64bit 上で書いている。えー 7 にしたんじゃないのー?と言われそうだが、諸事情により今日戻したのである(涙)。
戻してみたら、不思議なことに軽い。どういうわけか、今迄 Vista 上では使いものにならない状態だった SKKIME がさくさく動く。通常僕は Windows 上では「google 日本語入力」を使っていたのだけど、SKKIME が問題なく動くので、おそらくこの新生(新々生?)shannon に「google 日本語入力」を入れることはないだろう。
今、丁度音楽関係の環境を再構築しているところである。Cubase を入れて、プラグインの impulse response reverb や BBE、あるいは WAVES や Oxford のプラグイン、そして山のような楽器(と言ってもピアノとエレピとハモンド、それに信頼のおけるシンセが少しだが)を復元しなければならない。なんだかなあ……結局軽くなったので、まあいいんだけど。
負け惜しみで言うわけではないんだが、7 上で SUA を導入して環境を整備しようとしていたとき、python 絡みのソフトを使おうと思ったら pyconfig.h がない、と言われ、えー駄目じゃん、と一から Python を build しようとしていたのだが、どうにもらちが開かない。そういうことで、結局は 7 にしたメリットというと、軽くなったこと(これは今回 Vista に戻しても軽いのでもうどうでもいいんだけど)と XP mode が使えるようになったこと(ケータイの管理ソフトが 32 bit 環境でないと動かないのだが、これも管理に使わせてもらえる 32bit XP 端末があるので問題はない)位だったのだ。それもまあ、今になってみたら、特に惜しいと思わないでもいい状態になってしまった。
というわけで、しばらく(おそらくこの半年位かなあ)位は、このまま Vista 64 bit で音楽を作ることになりそうだ。
以前、Windows 7 Ultimate を入手した話を書いたけれど、あの後、手元にメディアが送られてきた。英語版なのだけど、オプションの言語パッケージを入れると(起動・終了時のメッセージなどを除いて)日本語版の OS と変わらない look and feel で使えるようになった。
TASCAM US-144 のドライバを入れる際にちょっと手間取ったが(再起動が早くかかるために、MIDI ドライバだけ入らないという現象が発生したが、上書きインストールを行うことで問題は解消した)、他はあまり問題らしい問題も発生していない。
一番の恩恵だと思えるのが、とにかく軽くなったこと。正直、ここまで軽くなるとは思っていなかった(勿論、パフォーマンスを最優先して Aero 等は全て殺してある)。そして、Windows Vista 64bit 上ではちゃんと動作してくれなかったSKKIMEが、何の問題もなく動作する。これは実に快適だ。
昨日 SUA も入れたし、これで少しは Windows の使用頻度も上がるかもしれない。
僕が、Linux 上での様々なことに GNU Emacs を使っているのはこれまでにも触れてきたけれど、最近どうもフォントが納得いかない、という気になってきた。
僕のように X Window System を使うのに慣れてしまっている場合、フォントの設定、というと、えーと、xfontselを立ち上げて……などとやってしまう。当然だけど、これだと X 用のビットマップフォントしか指定することができないわけで、フォントが満足いかないのはむしろ当然のことである。
最近の GNU Emacs は、FreeTypeとか Xft を使用することができるように書かれている。これは、昔は明示的にオプションで指定することが必要だった時期もあるのだけど、現在は configure が勝手に探してくれて include され、使うときも何も考えずに使えるようになっている……はずだ。ということで、.Xresources の Emacs に関する記述を以下のように変えてみる:
emacs*font: MigMix 1M
すると……おいおい、これぁちょっと巨大過ぎるなあ、ということで、
emacs*fontsize: 9
emacs.geometry: 80x40
emacs*font: MigMix 1M-9
としてみると……うん、まあいい感じなんじゃないでしょうか。

【後記】その後、MigMix の「背の高さ」が目につくようになったので、現在は VL ゴシックの 9ポイントで 80x50 の表示ということで落ち着いた。