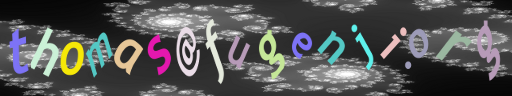かつてアスキーという出版社があった。今はアスキー・メディアワークスという会社になっているけれど、このアスキーの遺した大いなる遺産のおかげで、僕達は今でも Linux 上でのタイプセッティングを容易にできている。
Publishing TeX (pTeX) は、現在に至るまで、日本語を TeX で扱うためにはなくてはならないものである。僕も、論文を含む数多くの文書を LaTeX で組版してきたし、現在もほぼ日常的に LaTeX を使っているので、この pTeX なしにはそういった仕事に多大なる障害を来してしまうだろう。
しかし、pTeX には大きな負の側面もある。pTeX 成立以後の TeX における日本語環境の進歩が、ほぼ止まってしまったのである。これに関しては、この何年かの間に問題が表面化してきた。特に、レジスタの数が256に限定されていることは、大きな問題であるとされ、北川氏によるe-pTeXで拡張がなされるまで、皆の頭を悩ませた。
e-pTeX と、土村氏によるpTeXLiveによって、現在は問題なく TeX/LaTeX での日本語処理ができている状況ではあるのだが、世界の趨勢というのはこれを遥かに引き離して前進している。e-TeX によるレジスタの拡張だけではなく、pdfTeX の登場によるダイレクトな出力(これは Device Independent な中間出力という Knuth の方法論を超えているわけだが)の実現と microtypography の実装、そして UTF への数々の対応策と、それらの総決算とも言うべき LuaTeX の登場によって、ヨーロッパ系言語における TeX 環境は、日本語のそれとはもはや別次元と言ってもいいような状態になっている。
じゃあ、僕は今一体どうしているのか、というと、TeXLive 2010 上での日本語環境というのを試してはダメ、試してはダメ、というのを何度か繰り返していたのだけど、ついに、こういうプロジェクトが立ち上がったことを今日になって知ったのである:
http://sourceforge.jp/projects/luatex-ja/wiki/FrontPage
(LuaTeX-ja(仮称)プロジェクト)
ようやく、という感じである。今後に注目したい。僕の環境から pTeX が消える日が、着々と近付いているのである。
僕は Debian GNU/Linux というディストリビューションを使っているのだが、いくつかのツールはディストロの管理に依存せず、自分でソースを管理してビルドしている。これは昔からそうしていたから、というのと、やはりディストロのパッケージはカタくできているものなので、最新版を使っている場合にはこの方が都合がいいから、というのもある。
じゃあ具体的に何をそうしているのか、というと、まずは Kernel である。言うまでもなく、Kernel は Linux の中核を成すものなわけだけど、僕は定期的に kernel.org の finger server を覗くようにしていて、Kernel のアップデートがあったときにはアーカイブを落として、自分で debian package を作成している。
そして、GNU Emacs も自力でビルドしている。XEmacs が流行った頃に、GNU Emacs の cvs 版の方がいいなあ、という話をあちこちで聞き、当時はまだ電総研(現在の産総研)で公開されていたソースを落として build するようになって(それ以前も GNU からソースを取ってきてビルドしていたのだが)、それ以来自分で管理する習慣がついてしまった。一時期は Debian のパッケージを使ってみたこともあるのだが、現在は Bazaar で公開されているソースを落としてビルドしている。
Emacs 周辺のパッケージ、具体的には Mew, APEL, Emacs-w3n, FLIM, navi2ch, SKK, twittering-mode 等だが、これらも自分で管理している。具体的には anoncvs や Git でソースツリーを更新しつつ、定期的に自分でビルドしているわけだが、最近は Debian のパッケージを入れると、依存関係の解消のために不要なパッケージが入ってくるのが厭になってGit も自分でビルドするようになってしまった。こうなってくると、いちいち自力でやるのに一日何分かを費すことになるわけだ。
まあ、こう書くと、何をそんな面倒なことをやっているのか、と言われそうだけど、bash の強力なヒストリを使えば、そう入力に困ることはなかった。だから完全手動でやっていたのだけど、さすがにこれも面倒だし、暇があるときに一日に2度 Emacs のビルドをしていたりすると、ああこういうのがいかんのだよな、とか考えて自己嫌悪に陥る。そこで、shell script を書いて cron で自動実行するように整えた。これで一日に1度だけ、ネットワークも端末の負荷も軽い時間に、端末が自動的にその作業をしてくれるようになったわけだ。
本当は、こういうことをまず自動化できることこそが、Linux を使っていて便利なところのはずなんだけど……どうも、いかんな。
昨日のこと。ふと見た某オークションで、英語版の Windows 7 Ultimate が安価に出ていたのに、冗談半分でビッドしたところが、落札できてしまった。あれれ。こんなん買っていいのかなー、と、何やら後ろめたい思いを感じつつ、手続きを済ませた。
まあでも、必要と言えば必要なものなのだ。なにせ、Windows Vista は、7 が出たために以後のサービスパックを出していない(誤解なきよう書いておくけれど、サポートやパッチの配布は継続している)。一説には 7 は Vista SP3 相当だ、なんて話もある位である。
それに、7 のリリース直前に Microsoft 方面から聞いた話によると、たとえばエクスプローラのような頻繁に複数立ち上げるソフトのジョブを束ねることで、無用なリソースの食い潰しを防ぐ、というような配慮が 7 にはなされているという。まあ、話半分としても、試す価値がないわけではない。
それに、今使っている Vista 64bit は Home Basic で、いくつかのプログラムを使用できない。特に僕の場合に問題なのが、SUA が使用できないことだ。Windows 7 Ultimate ならば、これらの問題は皆解消される(はずだ)。
ただなあ……今回入手したのは英語版である。Windows 7 Ultimate は完全国際化されているので、インストール時に言語選択で日本語を選び、インストール後に拡張パックをインストールすれば日本語化できる(はずだ)。一応、関連情報の載っているサイトにリンクしておく:http://lowend.at.webry.info/200908/article_3.html
ちょっと環境の大掃除をする必要があって、Linux のシステムをクリーンインストールした。丁度今の時期は Debian GNU/Linux sid が不安定で、依存性が完全に解決していないライブラリがある状態で、正直こんな時期にこんな作業はしたくなかったのだが仕方ない。今は何とか以前の状態に戻せている。
で、折角なので、LaTeX を TeX Live 2010 ベースにしようと思って、ちょこちょこと作業をしていたのだけど……うーん。煮詰まった。OTF を入れて、dvipdfmx で日本語フォントを参照できるようにすると、盛大に文字化けする。何が問題なんだろうか。
さすがに TeX をハックする時間もないので、TeX Live 2009 + pTeXLive で環境を再構築する。まあこちらは方法を確立しているのでさくっと完了したわけだけど、この調子で LaTeX を使い続けていて大丈夫なのだろうか。pTeXLive も更新が止まっている→もう更新の必要なしと判断、のようだし。ううむ。