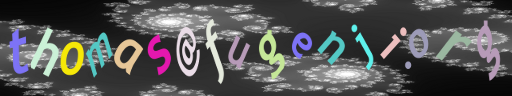pTeXLive インストール完了
ようやく babel 込みでpTeXLiveが使えるようになった。備忘録としてインストールプロセスをメモしておく。
まず TeXLive をインストールする。pTeXLive の最新版では目下 TeXLive の 2009 年度版をフォローしているので、まずはCTAN の historicからtexlive2009-20091107.iso.xzを取得する。unxz などで解凍した ISO image を、
mount -o loop ./texlive2009-20091107.iso /media/cdromなどとして mount し、/media/cdrom 内で、
install-tlを実行し、I を入力することでインストールが行われる。
インストールが終わったら、たとえば /tmp/ptexlive のように作業用のディレクトリを用意し、そこに以下のアーカイブを用意する:
- http://tutimura.ath.cx/~nob/tex/ptexlive/ptexlive-20100322.tar.gz
- eptex-100420.tar.bz2 (from http://sourceforge.jp/projects/eptex/wiki/FrontPage)
- http://sourceforge.jp/projects/eptex/wiki/FrontPage/attach/eptex-100420-patch1.diff
ptexlive-20100322.tar.gz と eptex-100420.tar.bz2 を展開したら、
patch -p0 < ./eptex-100420-patch1.diffとして eptex-100420 に patch を適用する。適用後、
cp ./eptex-100420/6babel.sh ./ptexlive-20100322として、babel の make に必要なスクリプトをコピーしておく。
次に pTeXLive のコンパイル設定を行う。
cp ./ptexlive-20100322/ptexlive.sample ./ptexlive.cfgとしておいてから、./ptexlive.cfg の編集を行う。僕の場合は:
### "ptexlive.sample"xindy はコンパイル上の問題があるという話があるので外したが、コンパイルしても問題ない、かもしれない。他は個々の環境に合わせて適宜調整する必要があるだろう。
### 推奨設定は先頭にまとめてあります。
### それ以外はコメントにしてあります。
### シェルスクリプトと同じで # 以降はコメントです。
### common.sh で自動判別している設定もあります。
### "../ptexlive.cfg" というファイルを作って、必要なものを書き写して下さい。
### "./ptexlive.cfg" や "../ptexlive.cfg.host名" でもかまいません。
### version 2010/ 3/22
### (必須・変更不可) ベースとなる TeX Live のバージョン
TEXLIVE_VERSION=2009
### (必須) mount した TeX Live 2009 DVD のディレクトリを指定
#ISO_DIR=/media/TeXLive2009
#ISO_DIR=/Volumes/TeXLive2009
ISO_DIR=/media/cdrom
### (任意) インストールした TeX Live 2009 のディレクトリを指定
# TEXLIVE_DIR=/usr/local/texlive/2009
# TEXLIVE_DIR=$ISO_DIR
### (任意) インストールする ptexlive のディレクトリを指定
# PREFIX=/usr/local/texlive/p2009
### (任意) 作業用ディレクトリを指定
# TMP_PREFIX=/dev/shm/ptexlive2009
# TMP_PREFIX=`pwd`/build
### (任意) make font でフォント検索するディレクトリを追加指定
# EXTRA_CMAP="/usr/local/cmap;/c/program files/cmap"
# EXTRA_TRUETYPE="/usr/local/ttf;/c/program files/truetype"
# EXTRA_OPENTYPE="/usr/local/otf;/c/program files/opentype"
EXTRA_TRUETYPE="/usr/share/fonts/truetype"
EXTRA_OPENTYPE="/usr/share/fonts/opentype"
### (任意) configure 時にキャッシュを用いる(高速化されるが実験的)
conf_option -C
### (任意) make 中に最大 N 個のプロセスを起動する(高速化)
### N は (コア数+1) にするのがよいらしい
# make_option -j 2 # for single core
make_option -j 3 # for 2 core
# make_option -j 5 # for 4 core
# make_option -j # unlimit
### (任意) configure に使うシェルを指定
export CONFIG_SHELL="/bin/bash"
### 余分にコンパイルするツールを指定する
### texdoc コマンドには luatex が必要
conf_option --enable-luatex
conf_option --enable-xetex
conf_option --enable-xdv2pdf
conf_option --enable-xdvipdfmx
conf_option --enable-dialog
conf_option --enable-pdfopen
conf_option --enable-ps2eps
conf_option --enable-psutils
conf_option --enable-t1utils
conf_option --enable-tpic2pdftex
conf_option --enable-vlna
# conf_option --enable-xindy
conf_option --enable-afm2pl
conf_option --enable-bibtex8
conf_option --enable-cjkutils
conf_option --enable-detex
conf_option --enable-devnag
conf_option --enable-dtl
conf_option --enable-dvi2tty
conf_option --enable-dvidvi
conf_option --enable-dviljk
conf_option --enable-dvipng
conf_option --enable-dvipos
conf_option --enable-lacheck
conf_option --enable-lcdf-typetools
conf_option --enable-musixflx
conf_option --enable-seetexk
conf_option --enable-tex4htk
conf_option --enable-ttf2pk
conf_option --enable-ttfdump
# ---------------------------------------------------------
### 既にライブラリが存在すれば、それを使う(高度な知識が必要)
# conf_option --with-system-zlib
# conf_option --with-system-libpng # using system-zlib
# conf_option --with-system-freetype2 # using system-zlib
# conf_option --with-system-gd # using system-libpng, system-freetype2
# conf_option --with-system-t1lib
# conf_option --with-system-freetype
# conf_option --with-system-xpdf
### libpng 1.4.0 以降は使えないので注意。
### OS 付属の freetype2 は pxdvi の縦書きに必要な otvalid モジュールが
### 無効になっていることが多いので注意。
### また '--with-system-gd' を指定すると '--with-system-libpng' と
### '--with-system-freetype2' も指定したことになる。
### kanji <=> unicode 変換に iconv を使う
conf_option --enable-kanji-iconv
### strip する(デバッグ情報を消して実行ファイルを小さくする)
STRIP=yes
### xdvi のツールキットを指定する
###(ディフォルトは自動選択、motif が最良の選択肢)
conf_option --with-xdvi-x-toolkit=motif
# conf_option --with-xdvi-x-toolkit=xaw
# conf_option --with-xdvi-x-toolkit=xaw3d
# conf_option --with-xdvi-x-toolkit=neXtaw
### X 環境がない場合
# conf_option --without-x
# conf_option --disable-xdvik
# conf_option --disable-pxdvik
### make (font|fonty|test) で xdvi と pxdvi を除外する
XDVI=echo
### make test で ps2pdf を除外する
PSPDF=echo
### ptex/platex コマンドの入出力文字コードを指定(ディフォルトは UTF8)
### nkf で自動変換するので、気にする必要はない
### 'UTF8' は ptexenc の独自拡張
KANJI_CODE=UTF8
# KANJI_CODE=EUC
# KANJI_CODE=SJIS
# KANJI_CODE=JIS
(以下変更なし)
ここまで準備ができたら、ptexlive-20100322 内で、
$ make all0と make を行い、問題がないようなら su → make install でインストール完了である。
$ ./6babel.sh
$ make otf
$ make fonty
$ make test
この手順でインストールできる pTeXLive は、最新版のひとつ前の version なのだが、やはり babel が使えないと困るので、現状ではこの手順でインストールを行っている。しかし…… ptetex3 のときと違って、dvipdfmx で作成した PDF の index が文字化けするんだなあ。さすがにここまでトレースする気力も時間もないので、今回は仕方ないということでこのまま使っているのだが。まあでも、とにかく babel 込みで pLaTeX が使えるだけでも有り難いので、まあこれはこれでいいことにしているのだった。
上のコンパイルで唯一外している xindy だが、あの後何度かコンパイルを試みているが一度も成功していない。依存関係がある clisp 周辺はパッケージを入れてコンパイルを試みたのだが、残念ながら結果は変わらない。→解決済み。『xindy の make 可能に』(2010年11月3日)を御参照のこと。