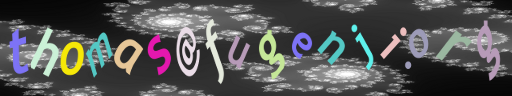僕は家では未だにADSLを使っている。マルチメディアをネットワーク経由で使うことが少ないからなのだけど、今回ははまってしまった。散々再起動を試みて、内部のリレーの動作音がしないので、あーこれぁあかんか、とプロバイダーのサポートに電話したら、担当者が僕の履歴を検索しながら、呆れたようにこう言ったのだった。
「いまのモデム、もう8年もお使いなんですね」
アナログ機器でも、特にモデムはそこそこ電圧もかかるし、壊れやすい物の上位に来るものなのは分かっているんだけど、まさかこのタイミングとは思わなかった。やれやれ。水曜日までケータイでしかアクセスできないとは。
最近、ちょっと環境の問題で音楽制作ができていない日々が続いているのだが、こうなると本当に Windows を起動する機会が減ってしまう。Steinberg CUBASE が Linux 上で動作して、ASIO をがっちりと Linux 上で扱えるならば、僕にとって Microsoft Windows というものの存在意義はゼロである。今の手持ちの VSTe / VSTi が使えなくなってもいいのだったら、早々に Mac に鞍替えしていてもいいはずだ。Mac OS X 上で生きていくことになったとしても、最近はMacPortsというものがあるし。
で……、時々聞かれることがある:「Linux、Linux って仰ってますけど、日常生活で必要なことに Windows がないと困るじゃないですか」否。web ブラウズは何も支障ないし、メールはどのみち Emacs 上で Mew を使うんだし、Microsoft Office なんて、余程必要のあるときしか使わない。これだって、plain text で書くか OpenOffice.org で書くかして、職場の Office にインポートしてフォントを揃える位しかすることはない。ああ、そうそう。あと一つだけ困るのは iTunes だなあ。まあ、MacOS の端末がひとつあればそれで済む話だし、それに手元の iPod だっていずれはiPodLinuxで使う日が来るかもしれない。
と、こんな話をしても Windows に慣れ親しんだ人々は納得しない。僕は、正規表現、ヒストリ、そしてヒストリの強力な検索・編集機能を有する shell は GUI に勝るんだ、という説明をさせられるはめになるわけだ。
いいですか、ここにファイルが100個あったとしますよね。で、そのファイルが 001 〜 100 という数字のファイルネームがついているとしましょう。もしこのファイルより古いファイルが36個見つかって、001 を 037 に、100 を 136 にしなきゃならないとして、Windows でそういうときはどうするんですか。ブラウザでひとつひとつファイル名を書き換えるんですか?もし僕だったらバッチファイル書いてやりますけどね、結局それって shell で CUI 使うってことじゃないですか。だから、GUI でマウスでやるから便利だというものでもないんだ、って、思いませんか?
……とか、書いて再現しているだけで腹が立ってきた。あー面倒だな。まあこういう人は放置するんだろう。でも、僕も shell に関しては少々困ったことがないわけでもない。僕が初めて触った UNIX は SunOS 4.1.1 だったから、標準の shell は csh だった。程なく NeXTSTEP を触るわけだけど、これの上でも csh だった。pure な csh というのは、実はあまり快適なものではない。勿論、エイリアスとかヒストリにおいては、Bourne Shell より優れていたわけだけど、僕が UNIX を使い出して程なく、世間では tcsh が流行り出して、僕も tcsh を使っている時期が長かった(ちなみに現在は専ら bash を使っております)。けれど、インタラクティブなユーザインターフェイスとして以外の shell としては、僕は早々に csh 系に見切りをつけたのだった。パイプとかリダイレクトとかを使い出したとたん、csh の挙動は僕にとって恐怖の対象になったからだ。少し経ってから、恐る恐る情報系の友人(彼は丁度その頃に Korn Shell に鞍替えして、へーコーンシェルねーあの頭のトンガってるやつでしょ、いやそれぁコーンヘッドだよ、とか下らない話をしていたのだったが)にこのことを聞いて、あーそれはね……と説明を受けて、あー俺はそんなに変なことを考えていたんじゃないんだ、と安心したのを今も覚えている。
で、まだ学生のときのこと。僕自身が強く必要になったわけではないのだけど、ひょんなことから、密度汎関数法というものをするために、自分の端末を使うことがあった。日本の材料科学の世界では、京大の足立裕彦名誉教授(当時はまだ教授だったけど)の開発されたDV-Xαという手法が非常に高い信頼をおかれていて、僕も研究会に入ってソースを入手した。で、インストールしようかなあ、と思って見てみると、DOSで散々ヤクザなことをしなければならないようになっている。こちとら貧乏研究者で、商用の FORTRAN なんて買えなかったので、当然のように f2c(当時は g77 もまだ信頼性が確立しておらず、当然 gfortran なんて存在しなかった)でやろうとしていたのだけど、あーそれなら UNIX 上でできるようにスクリプト整えたのがありますよ、と紹介されて、見てみたら、全部 csh script で書かれていて、天を仰いだ、なんてことがあったのだった。ビル・ジョイと某研究者に呪いの言葉を吐きながら、Bourne Shell に書き換えて、その後他のことでバタバタしていたので、結局これを DV-Xα 研究会にフィードバックしていない。就職してから、足立氏のグループが初学者向けの本にソースを CD-ROM で添付して出版していたけれど、あれの中に入っているのも、僕が呪った csh script のままのはずだ。
考えてみたら、その前にmxdorto使ったときも、たしか NeXT の absoft FORTRAN compiler でコンパイルしようとしたら COMMON 文のエラーが洪水みたいに出て、端末室で泣きながら書き直したんだった(今さっき Intel Fortran でコンパイルしたらなんと no error ! ただ do 文とかがどうも少しアヤしいような気もするなあ……ぶるぶるぶる、いや僕ぁもう書き直しませんよええ、そんな子犬みたいな目で見られても)。なんだか、僕の人生、こんなことばっかりのような気がしてきて、暗澹たる気分になってくるのだけど……なんだかなあ。
とうとう shannon(僕の Linux マシン……名前であるいは御想像の方がいるかもしれないが、 Dell のマシンなので Shannon と付けた)から Debian が供給している TeX Live 関連パッケージを全廃した。全面的に upTeX / upLaTeX に移行したのだ。前は英語だけ TeX 上で使えればあまり問題なかったのだけど、日本語とギリシャ語を使う必要が生じたので、upTeX / upLaTeX + Babel で処理することにしたわけだ。これでもはや何も問題がないような気になっていたのだけど、やはり気になるのが日本語のフォントである。
今迄、日本語に関しては、おそらくほとんどの方がされているのと同じ扱いをしていた。つまり、日本語以外のフォントは PDF に埋め込むけれど、日本語フォントだけは Adobe の font に任せてしまう、という方法である。まあ、PDF を表示・出力するほとんどの場合で Adobe Reader / Acrobat を使うことになるので、普通ならこれで問題はないわけだ。しかし、僕の場合は Ghostscript を使うケースが多いので、日本語フォントもできれば埋め込んでしまいたい。日本語のフォントで何か印刷に耐えるものを、と考えても、どうもあまりいい方法がない。
こういうことを書くと、「こんなことも知らないのか」という調子で Microsoft のフォントとか Adobe のフォントの埋め込み方を教えようとする人がいそうなので書いておくけれど、方法としてはそんなことはすぐにだってできる。そういうことを安易に他人に教えようとする輩は、Microsoft や Adobe のフォントの権利条項を読んだことがないはずで、両者共に、自社のシステム以外でそれらのフォント使用を許可しない、と明記していることを知らないのだろう。
xtt とかで表示に用いるんだったら、まあ本当はいけないんだけど、どうせこのマシン使うの俺だけだしい……とか言って MS 明朝とかメイリオとかを表示に使っている人が結構いるのだろう。僕は M+ と IPA フォントを合成したものを画面表示に使っている(ちなみに dual boot できる Windows Vista でも画面表示にはこれを使っている)。画面はこれで問題ないのだけど、僕の場合はフォントを埋め込んだ文書を配布する必要が生じることがある。こうなってくると厄介なわけだ。
実は、upTeX / upLaTeX では、日本語のフォント埋め込みは至極簡単にできるようになっている。/usr/local/teTeX/share/texmf/web2c/updmap.cfgで、
# kanjiEmbed {noEmbed|hiragino|kozuka|morisawa|ipa|etc..}
kanjiEmbed noEmbed
とあるのを、たとえば
kanjiEmbed ipaと書き換えて、mktexlsr → updmap-sys とでもやればいいだけだ。これで、dvipdfmx で PDF を生成すると IPA 明朝と IPA ゴシックが埋め込ませるようになる。しかし……実際に埋め込んでみると、やはり、
美しくない。美しい / 美しくない、などという言葉を使うだけで変だと思われそうだけど、TeX / LaTeX を使っている僕の知り合いの間では、少なくとも TeX / LaTeX に関しては、この言葉は重要な評価基準になるのだ。論より証拠、Adobe CID フォントの場合(Morisawa Passport を仕事用に所有している S に確認してもらったところ、このフォントは「小塚明朝 Pro」だとのこと)と、IPA フォントの場合の双方を見比べていただければいい。明らかに前者は後者より「美しい」のだ。ひょっとしたら、IPA の方が美しさに欠けるのは、Σのタタリかもしれないけれどね。はあ。しかし、どうしたものか。
……と悩んでいても仕方がない。あれこれ試してみたが、IPA ex明朝 / exゴシック 辺りなら使えそうなので、/usr/local/teTeX/share/texmf/fonts/map/dvipdfm/内の ptex-ipa.map と utf-ipa.map を基に、IPA ex明朝 / exゴシックフォントを参照するように書き換えた map ファイルを ptex-ipa2.map と utf-ipa2.map という名前で作成し、/usr/local/teTeX/share/texmf/web2c/updmap.cfgを、
# kanjiEmbed {noEmbed|hiragino|kozuka|morisawa|ipa|etc..}
# kanjiEmbed noEmbed
kanjiEmbed ipa2
と書き換えて、mktexlsr → updmap-sys としてみる。うまくフォントの埋め込みはできるのだけど、
** WARNING ** Glyph missing in font. (CID=138, code=0x0336)
というメッセージが……うーん。グリフのエラーということは、フォントにない文字があるのか。どうも困ったものだな……
前述の mixi のトピックは、生越氏が昔書いているような「情報乞食」の集団だと判断して、切り捨てることにした。「情報乞食」というのは、生越氏がもう十数年前に書いている文書に話が出てくるのだけど、該当部分を引用しておく:
このような善意で情報提供をしているような人を脱力させるような人は、はっきり言えばLinuxを使う資格なぞない。Linuxは誰に対しても平等に与えられている存在である。また、いわゆる「Linuxでメシを食ってる」類のサーバ屋等がその顧客に対している時を別にすれば、誰かが誰かに対して何らかの義務を負うようなものではない。つまり「お客さん」というものは存在していないのだ。
確かに情報を提供したり、ソフトを作ったりしている者と、それを使う人との間には、ある種の「立場の違い」は存在している。しかし、そうであればなおのこと、「利用者」は「提供者」に対して気を使うべきではないか? これが一般の製品なら、「利用者」は一定の対価を払って使っているわけであるから、「利用者=お客さん」である。しかし、Linux界ではそのようなことに対価を払っている人はいない。仮に「CD-ROMを購入」していたにしても、それは「対価を払った」ということにはならない。そうであるなら、「利用者」は単に「提供者」の善意にすがっているだけの存在に過ぎない。つまり、「お客さん」なんかではなく、「乞食」も同然の立場であるとわきまえるべきである。その「乞食」が「提供者」に対して「お客さん」のような気分になっているのを見ると、「お前は何様のつもりだ?」と言いたくなって来る。
これは別に「提供者は偉いんだ」ということを言っているのではない。あくまでも「お客さんなどという立場は存在しないのだ」ということを言っているに過ぎない。また、仮に「提供者は偉い」ということを言うにしても、Linuxはいつでも誰でも「提供者」になることが可能な世界である。そう誰もが当事者なのである。誰もが当事者であるが故に、「お客さん」という立場が存在してないとも言える。「単なる利用者は乞食のようなもの」と言われて悔しければ、それについて文句を言うのはなく、「提供者」になりさえすれば良いのだ。そして、その「提供者」には誰でもなれるのがLinuxである。
さて……で、件の乞食の集団トピックで最近しばしば目にするのが「ディスクトップ」なる、これまた意味不明の term である。明らかにこれは desktop デスクトップ の間違いなのだろうと思うけれど、この単語、僕の知らないうちに世間に定着してしまってやしないだろうか?ということで、google をつついてみると、
http://www.tt.rim.or.jp/~rudyard/gaigo001.html
なる文書が一番目に出てくる。この文書でディスクトップなる言葉が指摘されたのが2003年末だ、というから、つくづく日本人も馬鹿になったものではないか。
しかも、最近の google は もしかして:デスクトップ などと表示せず、「ディスクトップ」で検索をかけると直接「デスクトップ」の検索結果を合わせて表示するようになっている。これはどう捉えたらいいのだろうか……それだけこの面妖な単語が使われるようになっているということだろうか。なんだかねえ……