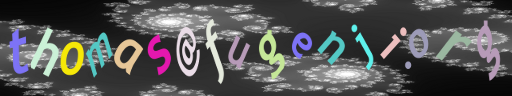僕の周囲には佃煮にする程ハカセと呼ばれる人間が存在する(いや、でも佃煮になんかしませんよ、ええ、だって僕も鍋に入らなきゃならなくなるので)。で、そのほとんどが、private の場で自分の学位に関して言及することを避ける。勿論、慎みとして、というか、「秘すれば花」というか、そういう矜持みたいなもので皆さんそうしているというのもあるだろうけれど、実のところ、学位を持っている、なんてことが知れると面倒なことが多いからだと思う。
例えば僕は、自分が学位を持っていることを結構何も気にせずに言うし、書く。別にそれで自分が権威化されるというわけでもないし、まぁそれなりの仕事をして、その間赤貧生活を過ごして、その上での学位なので、一応まぁ自分はこんなんですよ、というつもりで言い、書くのだけど、世間では最近この学位というやつに強い憎しみを向ける人が多くなったような気がする。その手の輩は、自分に都合のいいときはハカセとしての僕を「権威然として振舞うための拠所」として利用しようとして、僕にそれを拒絶される(当ったり前だよ、俺ぁそういうのが一等嫌ぇなんだ)と「学位くらいで偉ぶって」などと平気でのたまう。冗談じゃない。こっちは偉ぶってもいないし、そもそも学位持ってるから偉いなんてことが(ことにここ日本では)言えない、ということが骨身に沁みているから、とんだ冤罪なのである。で、これでもこちらが態度を変えないと「お前なんか『知的ワーキングプア』なんだろう」、とかのたまう。なら自分で学位取ってからそう言ってくれ、と思っていても言わないのは、それがいわゆる「言わぬが花」だからなのだけど、まぁ率直にいって馬鹿は確実に増殖している。
IT 関連で飯食ってる人々の中にも、こんなことも分からんのかなぁ、みたいな人が増殖しつつある(全体のレベルダウンではない……あえて言うなら「知的貧富の差の拡大」とでも言うべきだろうか、あるいは「志の差」とでもいうべきなのか)、という話を以前に書いたけれど、最近、いわゆる「暗黙の標準」に言及するときに "DeFacto Standard" などと書く人がいるのをよく目にする。
これは実は非常に「イタい」行為、というか、教養があるように振舞っていて、その実自分の無教養を晒している行為なのだけど、それを言うと瞬間湯沸かし器みたいに逆ギレされることが多いので、いい機会でもあるし、ここに文書化しておくことにする。
まず最初に、「暗黙の標準」というのは、欧米でよく書かれるところの de facto standard という表現を直訳したものである。見る人が見れば、"de facto" という部分が英語ではないことはすぐに分かる。もう少し敏い人ならば、これがラテン語であることがすぐに分かるはずだ。ではなぜ英語にラテン語が混じるのか。
いわゆる格調高い表現というやつには、大概古語か、あるいは学術的に権威の匂いを感じさせる外国語を差し挟むことが多い。日本語でも、(僕は日常の口頭表現でも使ってしまうのだけど)「そもそも」なんて言い出し方をすることがあるけれど、あれのもう少し大げさな場合を考えていただきたい。まぁ日本語の場合だったら、例えば論語の一節なんかを冒頭に引用して……
「子曰く、『学びて思はざれば即ち罔(くら)し、思ひて学ばざれば即ち殆(あやう)し』」などと言うけれど……
などと書き出すわけだ。
こういうものは勿論外国語にもある。それが、ラテン語を挟み込むことなのだ。特に英語圏では、学術用語としてのラテン語のステイタスははるか昔から確立している(たとえば Isaac Newton の “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” は、題名からしてすでにラテン語で書かれている)。英語だったら actual と書けばいいところを、わざわざラテン語で de facto と書くのは、そういった歴史的経緯を踏まえてよく行われる書き方のひとつに過ぎない。
だから、英語しか分からない人がこの言葉を見て、なんだぁよくわからんなぁ、と思うのだったら、「暗黙の標準」と日本語で書いておけばいいのである。生兵法は大怪我の本、などと言うけれど、肝心のラテン語の部分を変な風に書いては、せっかくの格調高さが仇となって、あーこいつ知らないのに無理して書いてるよ、という話になってしまうのだ。
そういえば、前にも書いたけど、以前にこんなことがあった。アメリカの fundamentalism(聖書根本主義)に関する話をネット上でしていたときに、
「fundamentalist は『レフト・ビハインド』を信じている」
と言われ、はぁ?となったことがあった。で、それは何ですか、と聞いた僕に得意げに返された説明は、どう読んでも携挙 rapture のことだとしか思えない。で、調べてみると、アメリカで大きな注目を集め、ドラマや映画にもなった "Left Behind" という小説があるらしい。内容は……あー、そういうことか。
僕は話の相手にこう書いた:「携挙のことを言ってるならそれは rapture でしょう」と。すると、日本では「レフト・ビハインド」と言うんだ、と、こう主張されたのである。おいおい、あなた、その『レフト・ビハインド』読みましたか?と聞くと、読んだし持っている、と堂々と言うのである。
この辺で何となく想像がついた方がおられるかもしれないが、この『レフト・ビハインド』なる小説、実は「携挙されそこなった」人達の混乱する様を描いた小説なのである。考えてみれば当然の話だ。"Left Behind" = 「取り残された」なんだから。僕は「レフト・ビハインド」という言葉は「携挙されそこなった」という意味であって、携挙はあくまで rapture であって、そんなところで変な和製英語を乱造しないでほしい、と書いた。すると、これは自然な言葉の経緯であって、自分が携挙を「レフト・ビハインド」と書くことは正しいのだ、と主張して譲らないのだ。
あいにく僕はカトリックなので、いわゆる千年王国の話には詳しくない(というか、物理的現象としての認識がない)。プロテスタントの知人に聞いてみると、「いや、携挙は携挙だし、それを英語で言うなら rapture だ」と言う。まぁそうだろう。僕もそう思う。しかしこの「レフト・ビハインド」氏、最後まで自説を取り下げることはなかったのだ。
無理して高尚な表現を使う必要はない。むしろ、使ったつもりで使えていなければ、己の知識の乏しさと慎みのなさを露呈するだけなのだ。しかし……この手の輩は本当に最近多くなっている。こういう「暗黙の知ったかぶり」汚染がこれ以上拡大しないことを祈るばかりである。