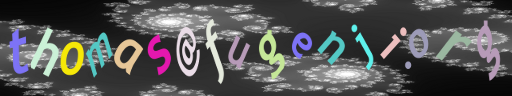備忘録。
Debian GNU/Linux (sid) の clamd に関して。どういうわけか daemon が起動しないのでアレレと思って調べてみたら、/etc/clamav/clamd.conf で:
LocalSocketGroup 20 Incorrect number of arguments
LocalSocketMode 20 Incorrect number of arguments
おいおいこれじゃ起動するわけないじゃん、ということで、ad hoc に、
LocalSocketGroup clamav
LocalSocketMode 660
と修正すると、daemon は問題なく起動。
ちょっとメールの設定をいじっていたら、下らないことでハマってしまった。ちょっとメモしておくことにしよう。
某民間プロバイダに接続するときの .mew.el の設定:
;; For SMTP
(setq mew-smtp-server "foo.bar.buz") ;; if not localhost
(setq mew-smtp-user "qux")
(setq mew-smtp-auth t)
(setq mew-smtp-port "587")
;(setq mew-smtp-auth-list 'CRAM-MD5)
最近はこの認証が一般的になっているんだけど、そんなことよりもさっさと APOP に対応しろや Yahoo!BB! Yahoo!メールのフリーアカウントはしれっと対応してるけどさ。
いままで Debian GNU/Linux のパッケージで入れてきたGNU Emacsだけど、どんなときもこれだけはソースから自力で build していたので、どうも気持ち悪くてならなかった。今日、ついに我慢の限界を感じて、自力で build したので、備忘録代わりに書いておくことにする。
まず Emacs のソースは anoncvs で cvs.savannah.gnu.org から取得。
$ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/sources/emacs co emacs
予め libjpeg, libtiff, libpng 等を整えておいて build。毎度のことながら何の問題もない…… configure 時に
CFLAGS="-O3 -pipe -combine -march=athlon64" (僕の環境の場合。他の方は -march option の選択に注意のこと)とする位か。
この後が意外と面倒だ。とりあえず日本語で読み書きできないと困るのでSKKを入れたいわけだけど、そのためにはまずAPELを入れておく必要がある。これは、
$ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/root login
(password: null)
$ cvs -z9 -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/root checkout apel
で取得。 m17n.org からは
FLIMと
SEMIも取得する必要があるので、
$ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/root login
(password: null)
$ cvs -z9 -d :pserver:anonymous@cvs.m17n.org:/cvs/root checkout -r flim-1_14 -d flim-1.14 flim
SEMI に関しては flim-1.14 に対応した最新版を、
http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~tomo/lemi/dist/semi/semi-1.14-for-flim-1.14/から取得する。
APEL, FLIM, SEMI のいずれも、make installのみでさくっとインストール完了。さて、そうしたら SKK である。辞書とかdbskkd-cdbは既に入っているので、ddskk のソースを入手して make --> make installでオーケー。ソースは、
$ cvs -d :pserver:guest@openlab.jp:/circus/cvsroot login
(password: "guest")
$ cvs -d :pserver:guest@openlab.jp:/circus/cvsroot checkout skk/main
で取得可能。ちなみに
skk/mainを
skkとすると、辞書から何から一切合切取得可能(少し考えれば分かりそうなものだけど)。
SKK が使えるようになったところで、必要なマクロを入れていく。
$ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.namazu.org:/storage/cvsroot login
(password: null)
$ cvs -d :pserver:anonymous@cvs.namazu.org:/storage/cvsroot co emacs-w3m
Emacs-w3m の cvs source には configure が入っておらず、configure.in しか入っていないので、
automake --> ./configure --> make --> make installの順で build。
Navi2chはこの sourceforge のページ通りに取得・build すればよろしい。
ちょっとアレレ、となったのが、Mewの cvs サーバに anonymous でアクセスできなくなっていること。これに関しては僕も詳細を知らない(最近まで Mew も Debian GNU/Linux のパッケージを使っていたので)のだけど、とりあえず Beta release の最新版を build する。
……と、こんな感じでもう使えるのだった。sdic も前に入れてあるし、英辞郎の辞書ファイルも使えるようにしてあるし。
ファイルシステムの選択という問題に悩む人は、今の世間ではかなりの少数派なのだろう。今時 FAT と NTFS の選択に悩む人はいないだろうし、Mac 関係者は何も考えずに HFS+ を使っているだろうし。しかし Linux の場合は、これはちょっと悩ましい問題ではある。
Linux 正調のファイルシステム、ということであるならば、現在の選択肢は Ext4 ということになるだろう。ほとんどの人はこの新しいジャーナリングファイルシステムを使用していると思う。しかし、このファイルシステムはまだ枯れ切っていない。技術革新イコール正義、みたいに思われているかもしれないコンピュータの世界では、実はこの「枯れている」という言葉が大きな意味を持つ。ダメな部分があらかた fix されきっている、という意味の「枯れている」という言葉は、魅力として大きいものなのである。
で、僕は現在 Ext4 ではなくて XFS というファイルシステムを使っている。このファイルシステムは旧 SGI が1990年代前半に開発したもので、ジャーナリングファイルシステムと呼ばれる安全性を重視したファイルシステムの中では最も古い、そして最も枯れているシステムのひとつである。このXFS、この 2010 年代になっても性能に優れた部分を数多く有しているということもあって、今使用しているシステムにはこちらを使うようにしてセットアップしたのである。
以前には ReiserFS というファイルシステムを使用していたこともある。これも1990年代半ばに使われるようになったファイルシステムだが、これは実は SELinux との併用が事実上不可能である上に、これの後継になるはずの Reiser4 FS が(コーディングのスタンダードを守っていないからだ、という説と、いやいや政治的な理由なんだよ、という説があるけれど、いずれにしても)未だに kernel tree に merge されていない。OS の動作の土台になるファイルシステムがこれではちょっと怖いので、僕は現在は全く使用していない。
で、XFS を使い始めての感想なのだけど……「ファイルの書き出しが遅い」これにつきる。具体的には kernel の build やそれに伴うファイルの書き出し・削除などをしているとき、とにかく時間がかかるのである。XFS はファイルの保護という観点では優秀なシステムなのだけど、動的性能に関して(悔しいことにこれ以外の点では優秀なだけに)日常レベルでも頭の痛いところである。次回にシステムをリファインするときには、Ext4 に戻すかもしれないが……うーん。困ったものである。今日も kenrel-2.6.33.2 をbuild しているところなのだけど……